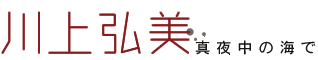 |
|
|
|
|
|
大学では生物を勉強した。
四年生になると卒業研究があり、希望する研究室で実験をさせてもらう。私の卒業研究は、ウニを使ったものだった。正確にいうならば、「ウニの精子のしっぽの運動性」。 なぜウニなのか。ウニの精子のしっぽが動くやりかたは、人の筋肉が動くしくみと、ものすごく似ているのだ。似ていて、もっと単純。そのうえ、ナマケモノの腹筋、だの、クジラの心臓(そういうものが人の筋肉と同じしくみで動くかどうかは知りませんが、実験というものは往々にしてそのような不思議な材料を必要とするものなのです)なんていうものにくらべれば、明らかに手に入りやすいものだったからだ。 ウニは高価じゃないか、とお思いになるかもしれない。いえいえ、ウニは無料だったのです。ウニを、わたしたちは、潮がいちばん引く時間に、拾いにゆくのだ。それはなぜだか、たいがい真夜中だった。海岸は、まっくらだった。カンテラのくっついたヘルメットをかぶり、ゴム引きのひざ上までくる長靴をはき、ぬれてもいいジャージを着て、わたしたちは浅瀬に入る。カンテラに照らされた幾十ものウニが、砂の上にみえる。ちっぽけな茶色いバフンウニだった。食用になる立派なウニは、漁協の許可を得て採らなければならない。わたしたちが使うウニは、浜辺のゴミにしかみえないものだった。惜しげもなくバケツに放り入れた。すぐに大きなバケツ三杯ほどがいっぱいになった。 実験室に帰ると、いそいでビーカーを山ほど用意した。それから、海水を満たしたビーカーの上にウニを一匹のせた。ちょうどふちのところにのっかって落ちないでいてくれるくらいの、小さなビーカーである。 さて、すべてのウニを放精させてしまうと、わたしたちはふたたびウニをバケツに入れ、暗い海に向かう。精子を出してくれた後のウニを、もといた場所に戻しにゆくためだ。 |
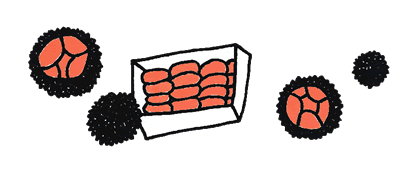
|
| かわかみひろみ◎1958年4月1日東京生まれ。お茶の水女子大学理学部生物学科卒業。中学・高校の理科教員を経て94年「神様」でパスカル短編文学新人賞を受賞、そして作家デビュー。96年「蛇を踏む」で第115回芥川賞を受賞。そのほか著書に『神様』(ドゥマゴ文学賞、紫式部賞)、『溺レる』(伊藤整文学賞、女流文学賞)、『椰子・椰子』、『センセイの鞄』(谷崎潤一郎賞)、『光ってみえるもの、あれは』など。 |
| 絵=中村久美 |
|
Copyright (C) 2005 NAKAJIMASUISAN Co., Ltd.
|
|