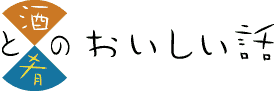 |
|
|
|
|
|
|
|
|
鮭の水煮缶に、一本、良くて二本、挟まっている、鮭の背骨。 二本あると、とてもうれしい。小さかった頃、うちではたいてい、その缶を開けた(つまり、ちょっぴりでも御飯の支度の手伝いをした)子に与えられる御褒美だった。 その食卓では、小皿に取り分けた自分用の骨。ほろり、そくそくっと、くずれる歯当たりに、陶然として、小首傾げたものだ。だから、一人っ子が羨ましかった。鮭缶の度に、その快感を独り占めできるのだから。 鮭缶。今は昔の、かつての御馳走。一缶を四人で。貧しかった。どうしてあんなに、びっちり鮭の身を詰めることが出来るのか。缶を開けるや、なるべく身を崩さずに、小鉢へ移すのが、第一関門。それから、先の細い箸で、慎重に、身を開き、骨を取り出す。この時あせると、脊髄が折れ枝骨も多く欠損し、がっかりすることになる。どうせ噛みしだいてしまうものなのに、すこしでも完璧に近い形で「採掘」するのが、自己に課した任務。そして、なにごともなかったかのように、身を合体修復し、この作業は達成する。 「鮭の中骨缶」の存在を知ったのは、大人になってからだ。缶を開けると、さけほねさけほねさけほねが、折り重なって、ぎゅぎゅっと詰まっている。身沢山で、骨も、ごっつ太く、節の間の半透明の骨髄の玉も、ぷるるんとして勢いがあり、じつにたくましい。 でも、違う。一缶に一本か二本の、ほろほろとした、かそけきたたずまいが、そそる。あの風情こそが、貴重な肴の味なのだ。 |
|
 |
|
|
杉浦日向子◎文筆家。現在、NHK総合テレビ「お江戸でござる」で活躍中。
|
|
Copyright (C) 2002 NAKAJIMASUISAN Co., Ltd.
|
|